
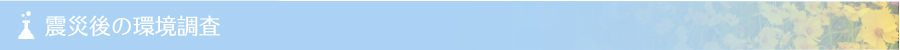
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と、それに引き続く大津波により、三陸沿岸部は甚大な被害がもたらされた。東北大学では震災前から気仙沼市〜石巻市の沿岸地域で出生コホート調査を進めていたが、震災により調査は中断を余儀なくされた。震災直後はまず医療機関や自治体への支援物資輸送などの活動の一翼を担っていたが、事前の準備もなく震災に直面し、何を行うべきなのか、手探りの状態で忙しく動き回っていた時期であった。
4月に入り、支援物資は順調に被災地に配分され、災害医療も体制が整ってきたものの、被災地の環境は依然として厳しい条件に置かれていた(アルバム 調査地の復旧・復興の様子を参照)。何よりも、津波により打ち上げられた海由来の底泥、石油基地などから流出した重油などが津波被災地に堆積しており(震災で打ち上げられた底泥を参照)、悪臭が蔓延し、乾燥し粉じんとして飛散する様子が観察された。
津波は、陸上から家屋・工場などを海に引きずり込むとともに、海の底泥を大量に陸地に運び上げた(津波汚泥)。被災地に堆積した底泥の量は膨大であり、また港湾近くの底泥と、外海に面した地域の底泥では見た目でも明らかに性質も異なっていた。さらに、乾燥とともに粉じんとして舞い上がり、拡散するとともに、口や鼻から体内に取り込まれることも懸念された。その底泥にはどのような化学物質が含まれているのか、人への曝露が懸念されるのか、健康影響が懸念されるのか、環境調査が必要と考えられた。
そこで、震災前から東北沿岸部で環境調査を行っていた研究チームに相談し、気仙沼市を中心として、三陸沿岸部を対象とする環境調査を開始した。主な目的は、1)底泥および環境生物中の化学物質の網羅的解析、2)その地理的分布と時間的推移、3)環境汚染が大きい場合に、人体汚染があるのかどうかの検証、4) 復興・土壌修復による汚染低減効果の検証、5)汚染の未来予測、などである。その後、自治体よりガレキ仮置き場の環境調査の相談を受け、6)ガレキ置き場のモニタリングを追加した。環境調査を行う上で、一部の環境試料については、震災前に採取した対照試料を保有しており、震災後の試料と比較が可能なこと、さらに現地に東北大学の事務所があったことが調査を実行する上で大きなポイントとなった。
さて、環境調査については、当時を振り返ると、まず何を調査すべきなのかわからなかった。さらに、環境調査の前にまず被災者支援を行うことが優先のようにも思われ、環境調査を行うには倫理的にも物理的にも時期尚早と考えられた。このため最初の環境調査を行ったのは6月上旬であった。従って、災害直後の環境試料の採取は行っていない。この点は、津波被害に関する環境評価において弱点と思われ、未だに「当時、何を行うべきだったのだろうか」と反芻する。もし仮に、将来において同じような大災害に直面した場合、支援物資の配送という人道的支援が最優先と考えられるものの、長期的な対策を構築するためにも、是非とも環境評価を初動から実施すべきと考える。そのような準備を平常時から行っておくべきなのだろう。南海トラフ地震や首都直下地震は避けられない現象と考えられ、東日本大震災をはるかに上回る規模の被害が生ずる可能性も指摘されている。未来に起こるであろう大災害に備える上での教訓は何か、そのことを伝えることも意識しながら、我々の調査結果を紹介したい。
なお、本研究は「三井物産環境基金 2011年度 東日本大震災 復興助成(研究助成)」の支援を手がかりに開始した調査研究である。当初は各研究者の個人負担に依拠したが、本格的な調査には限界があった。その中で、三井物産より極めて迅速に研究支援が開始され、調査を継続する力となったことをここに記し、感謝としたい。